就職・転職活動は「運」に左右されるものだ、とよく言われます。「就活は運ゲー」というフレーズも耳にします。しかし、本当にそれだけでしょうか?もちろん景気動向や競争相手との巡り合わせなど運の要素もありますが、実は自分の行動習慣次第で内定の確率を大きく高めることができるのです。
たしかにキャリア理論では「計画された偶発性理論」(クランボルツ, 1999)という考え方があり、キャリアの約8割は予測不能な偶然の出来事に左右されるとされています。しかし同時にこの理論は、好奇心・持続性・楽観性・柔軟性・冒険心という5つの行動特性を身につけることで「偶然」を味方にできると説いています。要するに、運任せではなく自分から行動を起こすことで“運すら引き寄せる”ことが可能なのです。
以下では、大学生の新卒就活でも社会人の転職活動でも役立つ、成功確率を高める5つの行動習慣をご紹介します。それぞれの習慣について、国内外の研究データに裏付けられた効果と具体的な実践例をわかりやすく解説します。これらを実践すれば、「就活は実力ゲー」に変えられるはずです。
綿密な準備と計画:先手必勝で臨む
「就活は計画が9割」と言っても過言ではありません。闇雲に応募を始めるのではなく、まず戦略を立てて綿密に準備する習慣が、成功率を左右します。具体的には自己分析で自分の強み・適性・価値観を洗い出し、志望業界や企業研究を徹底的に行います。また、エントリーや選考のスケジュールを把握し、早めに就活を開始することも重要です。実際、大学生の大規模調査では、偏差値が高くない大学の学生ほど就活開始が遅く応募社数が少ない傾向が見られ、これが就職で苦戦する一因と指摘されています。反対に、早期から計画的に動いた学生は内定率が高まる傾向にありました。
準備に時間をかけられる分、エントリーシートや履歴書の質も上がり、面接対策も十分にできます。
また、自分の目指す方向性を明確にすることも大切です。目標や軸がはっきりしている人ほど良い結果を得やすいことが研究から示されています。例えば中国で行われた研究では、就職活動における目標の明確さが高い人ほど、再就職後の満足度や給与といった「質」の面でも優れた結果を得ていました。単に場当たり的に応募するのではなく、どんな仕事に就きたいのか、何を自分の売りにするのかを明確にして計画を立てることで、面接官にも熱意と一貫性が伝わりやすくなります。
さらに、就活の「行動量」も重要です。過去378件の研究をまとめたメタ分析によれば、求人情報の収集や応募などの就職活動強度が高い人ほど、面接や内定をより多く獲得できることが確認されています。行動量を増やすためにも計画的なスケジューリングが不可欠です。
実践例(学生): 3年生の夏頃から自己分析シートを書き始め、志望企業リストと選考スケジュール表を作成しておく。企業ごとに研究した内容をノートにまとめ、エントリー開始に合わせて準備万端で臨む。
実践例(転職): 転職を思い立ったら在職中でも早めに業界動向や求人情報のリサーチを開始する。履歴書・職務経歴書を更新し、自分の経験を棚卸ししておく。応募スケジュールを逆算し、いつまでに現職を退職するか計画を立てる。
人脈づくりと支援活用:情報と機会を引き寄せる
人との繋がりを広げて活用する習慣も、就活・転職成功率を高める大きなポイントです。多くの求人は公には出回らない「隠れ求人」だったり、社員や知人の紹介で採用が決まることがあります。「It’s not what you know, but who you know(何を知っているかではなく、誰を知っているか)」という言葉があるように、コネクションは侮れません。実際、米国の古典的な研究では「知人や旧友など弱いつながりから得た情報」が就職に最も有用であることが示されています。
有名なGranovetterの調査(1973年)によると、職探しにおいて親しい友人よりもむしろ普段あまり会わない知人から得た紹介の方が採用に結びつきやすかったのです。同様に、最新の**LinkedInを使った実験研究(2022年)でも、緩やかなつながり(弱いつながり)を持つ相手の紹介ほど新しい仕事に結びつく可能性が高いことが確認されています。
日本でも、大学のOB・OG訪問や企業説明会での人脈づくりが内定獲得に寄与するケースが多々あります。また、大学のキャリアセンターなど公的支援を積極的に活用することも有効です。小杉 (2008年) の調査によれば、大学の就職支援サービスを上手に活用した学生は就職率が明らかに高まる傾向が見られています。支援スタッフから応募書類の添削や模擬面接指導を受けたり、企業とのマッチング機会を紹介してもらえるためです。
社会人の転職でもエージェントやハローワーク、業界のコミュニティを活用することで、自分では見つけにくい求人情報を入手したり、推薦を受けたりできる可能性が高まります。人との繋がりは情報やチャンスの宝庫ですから、日頃からネットワーキングを習慣づけておきましょう。
実践例(学生): 大学のOB/OG訪問を積極的に行い、志望業界で働く先輩からアドバイスをもらう。キャリア支援課のセミナーや合同企業説明会に参加して企業の人事担当者と名刺交換しておく。
実践例(転職): 前職・現職の同僚や取引先に転職を検討している旨を伝え、社内公募や知人紹介の求人がないか情報収集する。LinkedInなどプロフェッショナル向けSNSで業界の人と繋がり、動向や求人の紹介を依頼する。転職エージェントに登録して非公開求人を紹介してもらう。
スキルアップと自己研鑽:市場価値を高める

継続的に学習しスキルアップする習慣も、長い目で見て就職・転職の成功確率を上げます。企業は即戦力やポテンシャルの高い人材を求めており、「この人は成長し続けそうだ」「時代に合わせてスキルを磨ける人だ」と評価されれば採用可能性が高まります。学生であれば在学中の勉強はもちろん、語学検定やIT資格取得、インターンシップ参加などで専門性や実践経験を積むことが有利に働きます
転職希望者であれば、業務の傍ら新しい技術や知識を習得する、自主的に資格取得やセミナー参加をするなど、「学び続ける姿勢」を示すことが大切です。
エビデンスもこれを裏付けています。内閣府(2018年)の分析では、失業中の人が自己啓発(職業訓練や資格勉強など)を行うと、行わなかった場合に比べて再就職できる確率が10~14%ポイントも向上することが示唆されています。
つまり、ブランク期間に学習に励んだ人の方が早く職に就いているのです。また、カナダの研究(2020年)では「ラーニング・マインドセット(学び続ける姿勢)」を持つ社会人ほど、その後のキャリアで客観的な成功(昇進回数が多い等)と主観的な成功(仕事満足度が高い等)の両方を達成しやすいと報告されています。
継続的な学習が業務能力を高めるだけでなく、自信や意欲にも繋がり、結果的にキャリア全般で良い成果をもたらすということです。
これらの事実は、「就活・転職中こそ学ぶことを止めない」ことの重要性を教えてくれます。面接でも「最近〇〇の資格取得の勉強をしています」「独学で△△のスキルを習得しました」と話せれば、熱意や向上心のアピールになります。逆に何も学んでいない人は時間を無為に過ごしているように見え、評価で差がついてしまいます。スキルアップの習慣は、将来の自分への投資と考えましょう。
実践例(学生): 興味のある分野で資格取得に挑戦する(例:TOEICや基本情報技術者試験など)。長期インターンシップやボランティアに参加して、実社会で通用するスキルや職務経験を積む。業界研究として関連する専門書や論文を読む習慣をつける。
実践例(転職): 就業後や週末にオンライン講座で最新技術や業務知識を学ぶ(例:プログラミング講座、データ分析の研修など)。業務に関連する資格試験に挑戦し、履歴書に書けるスキルを増やす。社外の勉強会や業界セミナーに参加して自己研鑽と人脈構築を同時に行う。
目標設定と自己管理:計画的に動きPDCAを回す
明確な目標設定と自己管理(セルフマネジメント)の習慣は、就活プロセスを効率的かつ効果的に進めるうえで欠かせません。ただ闇雲に応募を続けるより、「1週間で〇社エントリーする」「今月中に〇回は模擬面接を受ける」など具体的な行動目標を立てて遂行する方がモチベーションを維持しやすく、結果も出やすくなります。心理学の研究でも、目標を設定して計画的に行動することで自己効力感が高まり、行動量が増えることが知られています。
実際、求職スキルに関する介入研究のメタ分析(Liuら, 2014)によれば、職探しセミナーやワークショップなど何らかのトレーニングを受けた求職者は、受けていない人に比べて約2.67倍も就職に成功しやすかったと報告されています。
特に、そうしたプログラムの中でも目標設定や積極性の促進、計画的な行動指導を含むものは効果が高かったことが分かっています。
つまり、自分で目標を決め進捗を管理するスキルを身につけると、それだけ内定に近づくということです。
また、定期的な振り返り(レビュー)も自己管理の重要なポイントです。一度立てた計画をやりっぱなしにするのではなく、定期的に進捗をチェックし、必要に応じて作戦を修正しましょう。応募して書類選考が通らなければ応募書類の内容を見直す、面接でうまく答えられなかった質問があれば答えを準備しておく、といったPDCAサイクルを回すことで、回を追うごとに成功率が上がっていきます。研究でも、模擬面接の練習においてフィードバックを受けた求職者は、練習のみの場合に比べてその後の本番面接パフォーマンスが向上したとの結果が出ています
自分では気づかなかった改善点を指摘してもらうことで飛躍的に成長できるのです。
(例1)
毎週末にその週の就活進捗を自己チェックし、予定未達の場合は翌週に巻き返す計画を立てる。また、達成できた場合は自分にご褒美を与えてモチベーション維持に繋げる。
(例2)
応募先ごとにExcelなどで進捗管理表を作成する。企業名、応募日、面接日程、結果、反省点などを書き込み、常に全体像を把握することで抜け漏れを防ぐ。
(例3)
面接練習を友人やキャリアアドバイザーにお願いし、フィードバックをもとに回答内容や話し方を修正する。例えば「志望動機が抽象的」と指摘されたら具体例を盛り込むよう改善し、次の面接に活かす。
前向きなマインドセットと継続力:折れない心で挑み続ける
最後に、ポジティブなマインドセットと粘り強さを持つ習慣です。就活では誰しも不採用通知をもらったり、思うように進まない時期があります。その際に「自分はダメだ」「もう諦めよう」と後ろ向きになるのではなく、「今回は縁がなかっただけ」「次はきっとうまくいく」と前向きに捉えて挑戦を続けることが、成功への大きなカギとなります。
実はこの楽観的・積極的な姿勢が本当に功を奏することは、研究でも明らかになっています。たとえば、MBA学生を対象とした楽観性に関する追跡調査研究では、楽観的な性格の人は悲観的な人に比べて、同等の能力であっても就職活動で明らかに良い結果を出していました。
具体的には、楽観的な人は悲観的な人よりも短期間で複数のオファーを獲得し、より自分の希望に合った仕事を選び取る傾向があったのです。研究者らは、楽観的な人は自己効力感が高く多少の困難にもめげず行動を継続するため、結果的に成功率が上がると分析しています。
また、ストレス対処法を持っているかどうかも重要です。フィンランドの研究では、事前に失敗や拒否される可能性を想定し、その際の対処策を計画しておくことで、就活中のメンタルを安定させモチベーションを持続できると報告されています
例えば「お祈りメール(不採用通知)をもらったら一日落ち込む時間を作るが、翌日には気持ちを切り替えて次に臨む」「疲れたら友人に愚痴を聞いてもらいストレス発散する」等、自分なりのリセット方法を用意しておくと良いでしょう。心が折れて活動を休止してしまうと機会損失に繋がります。多少運が悪い局面でも、続ける人にはいずれチャンスが巡ってくるものです。実際、「計画された偶発性理論」を提唱したクランボルツ教授も、思わぬチャンスを活かすには楽観性と持続性(粘り強さ)が欠かせない資質だと述べています。
ポジティブなマインドセットは面接での態度にも表れます。明るくハキハキと振る舞い、自信ありげに自己PRする候補者は魅力的に映りますし、仮に最初は多少空回りしても「この人は伸びそうだ」と評価されることもあります。反対に自信なさげで消極的だと、優秀でも「うちに入りたい熱意がなさそう」と見なされてしまいます。気持ちが落ち込んだときこそ意識的に笑顔を作り、前を向くようにしましょう。
(例1)
不採用通知が来ても「ご縁がなかっただけ」と割り切り、気持ちを切り替えるルーティンを決めておく(例:好きなスイーツを食べる、一晩寝たら忘れる等)。このようにして失敗を引きずらない習慣を作る。
(例2)
日記や就活ノートに、毎日取り組んだことや良かった点を書き出す。小さな前進でも記録することで達成感を得て、自分を肯定できるようにする。ポジティブなセルフトーク(自己対話)を心がけ、「自分ならできる」と自分を励ます。
(例3)
面接で緊張や不安を感じても、「自分を雇うことで会社にメリットを提供できるはずだ」と信じて堂々と話すように意識する。仮に過去に失敗した質問が出ても、「今回は大丈夫」と自分に言い聞かせて臨む。
まとめ:運を味方に、実力で道を拓こう
就職活動・転職活動は確かに運の要素もあります。しかし、ここまで紹介した5つの行動習慣(「綿密な準備と計画」「人脈づくりと支援活用」「スキルアップと自己研鑽」「目標設定と自己管理」「前向きなマインドセットと継続力」)を実践すれば、その運を自分の味方につけ、採用成功の確率を大きく高めることができます。単に闇雲に運任せで動くのではなく、エビデンスに基づいた賢い努力を積み重ねることで、結果は着実についてくるでしょう。
「運ゲー」と割り切ってしまえば気持ちは楽になるかもしれませんが、それでは改善も成長もありません。一方、「実力ゲー」と捉えて主体的に行動すれば、自分の成長を実感できますし、たとえすぐに結果が出なくても次に繋がる経験値が確実に蓄積します。
最後にお伝えしたいのは、どんな状況でも決してあきらめないで一歩を踏み出し続けてほしいということです。紹介した行動習慣は、実践し始めれば最初は少し大変かもしれません。しかし、習慣になってしまえばこちらのもの。努力が積み重なって「偶然のチャンス」を呼び込み、周囲からは「運がいい人」に見える日が必ず来ます。ぜひ今日からできることに取り組んで、「運を実力で掴み取る」就活・転職にチャレンジしてみてください。応援しています!
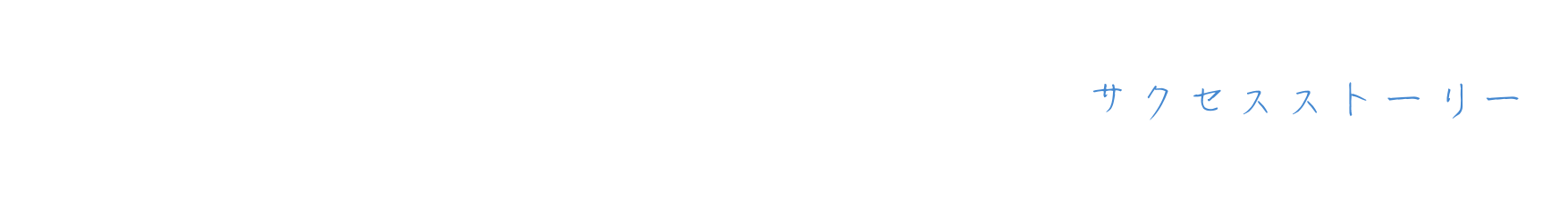
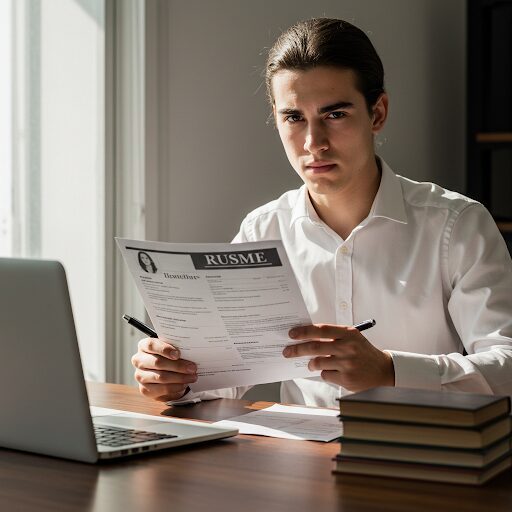


コメント