転職活動をするとき、多くの人が直面するのが「希望年収の設定」です。希望年収が高すぎると採用されにくくなる一方で、低すぎると自身の市場価値を下げる可能性があります。では、転職者は実際にどのようにして希望年収を決めているのでしょうか?阿部正浩氏(2016)は約1,200人の転職経験者を対象にした『ワーキングパーソン調査2014』のデータを用いて、希望年収の決定要因を実証的に分析しました。本記事ではその研究結果を簡潔に解説します。

希望年収の設定に最も影響するのは前職年収
阿部氏の研究では、前職年収が希望年収の設定に与える影響は非常に大きく、1%前職年収が高いと、希望年収は平均で約0.41%上昇することが明らかになりました。この傾向は特に在職中に転職活動を行う層で顕著で、On the Job Searchのグループではその影響度が0.53とさらに高くなっています。
前職年収が高い人ほど、希望年収も高くなる
転職活動の状況によって異なる希望年収
失業してから転職活動をする人と、在職中に転職活動をする人では希望年収の決め方が異なります。失業者のグループでは、前職年収の影響度が0.35に留まり、希望年収はより保守的に設定される傾向があります。背景には、無収入状態であることによるリスク回避行動があると考えられます。
在職中に転職する人の方が、希望年収を高く設定しやすい
退職理由が希望年収に及ぼす影響
退職理由によっても希望年収の設定には明確な差が見られました。たとえば、「賃金への不満」で退職した人は、契約期間満了で辞めた人に比べて希望年収を平均19%高く設定しています。「仕事上の不満」「会社都合」の場合も、それぞれ11%前後の上昇が観察されました。つまり、不満を感じていた人ほど、次の職場ではより良い待遇を求めているという傾向がデータから読み取れます。
前職に不満がある人ほど、高い希望年収を掲げやすい
希望年収と実際の年収のギャップ
転職1年後の年収(決定年収)は、希望年収より平均で約9%低くなる傾向があります。On the Job Searchの人ではこのギャップはわずか1%未満(係数0.99)で済んでいますが、失業してからの転職者では希望年収に対する実際の年収の係数が0.90となり、約1割低く抑えられることがわかりました。
希望より実際の年収は平均1割低くなりやすい
希望年収が高いほど失業期間が短い理由
希望年収と失業期間との関係にも注目です。希望年収が高い人ほど、職探し期間が短くなる傾向があります(失業者グループにおける係数は有意な負の値)。これは、高い希望年収を掲げる人が優秀である、もしくは明確な自己評価と積極的な求職活動を行っていることを示唆しています。なお、On the Job Searchの層では逆に希望年収が高い人ほど転職活動が長引く傾向も確認されています。
希望年収が高い人ほど、短期間で転職を決めている傾向がある
入職経路ごとの希望年収の違い
どのような経路で転職先を見つけたかによっても、希望年収には差が生じます。ハローワーク利用者の希望年収は全体平均より13%低く、無料求人誌では17%、チラシでは同じく17%も低くなる傾向があります。一方で、直接企業に応募した人の希望年収は他と比較して高く、前職年収に対する希望年収の弾力性が0.65と非常に高くなっています。
転職手段によって、希望年収の高さに明確な差が出る
まとめ
阿部氏の研究からは、希望年収の決定に影響する具体的な数値が明確に示されました。前職年収、転職活動の状況、退職理由、入職経路といった複数の変数が複雑に絡み合いながらも、一定のパターンが存在しています。転職を成功させるためには、データに基づいた現実的かつ戦略的な希望年収の設定が鍵を握ると言えるでしょう。
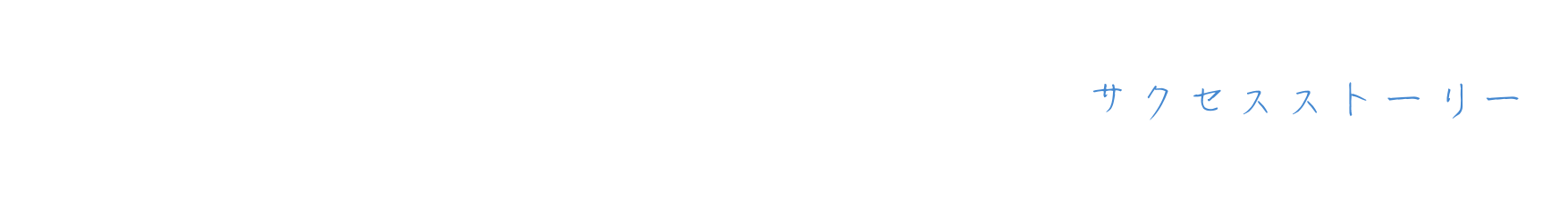




コメント