かつて日本では、「大企業に入社すれば一生安泰」という神話が広く信じられていました。高度経済成長期には、大企業への就職は高収入と雇用の安定を約束し、終身雇用と年功序列のもとで会社が社員の生活を守るという暗黙の了解がありました。
しかし、現代の若者はこうした昔ながらの前提に疑問を抱き、大企業に就職しても心から「安心」できないと感じる傾向があります。それはなぜでしょうか。本稿では、若者のキャリア観や価値観の変化、雇用システムの転換、働き方の多様化、自己実現志向とのギャップ、若者が抱える不安の実態を分析し、現代における「安心」の再定義を試みます。
若者のキャリア観と「安定」への価値観の変化(日本・海外)
まず、若者のキャリア観自体が大きく変化しています。日本の若者は「経済的豊かさよりも楽しい生活を重視」する傾向が強まり仕事選びでも「自分の能力や個性を発揮できること」を重んじています
大企業で安定を得ることよりも、仕事そのものの楽しさや自己成長を重視する価値観が広がっているのです。また、Z世代(おおむね1990年代後半〜2000年代生まれ)は「自己実現」と仕事の社会的意義を重視し、単に経済的報酬を得るだけでは満足できない傾向があります。
彼らは社会への良い影響や個人の成長を実感できる仕事を求めており、価値観が以前の世代とは明確に異なると指摘されています。
一方で、「安定」そのものへの考え方も多様化しています。依然として就職先に安定を求める声は根強く、2022年の調査では新卒学生の企業選びのポイント第1位が「安定していること」(43.9%)でした。しかし、その「安定」の捉え方は変わりつつあります。例えば大企業志向は近年低下傾向にあり、2023年卒学生では大手企業を志望する割合が48.5%と過半数を割りました。これは過去最高だった数年前から減少傾向にあります。
代わりに中堅・中小志向が増えつつあり、必ずしも「大手=安定」と一辺倒に考えない学生も増えているのです。
海外に目を向けても、ミレニアル世代やZ世代の多くは仕事の目的や意義を重視するようになっています。Deloitteの世界調査(2024)によれば、ほぼ全てのZ世代・ミレニアル世代が「目的志向の仕事」を求めており、自分の価値観と合わない仕事は平気で断るといいます
また、「給与よりやりがい」「安定より成長」という価値観も広がり、若年層はどの国でも過去より職業選択の基準が多元化しているのです
総じて言えば、現代の若者にとって「安定」とは単に一つの会社に居続けることではなく、自分らしく成長し続けられることや仕事に意味を見いだせることまで含む広い概念になりつつあります。
日本型雇用システムの変容:終身雇用・年功序列の崩壊
若者が大企業にいても安心できない背景には、日本型雇用慣行そのものの揺らぎがあります。高度成長期から長らく、日本企業は新卒一括採用・終身雇用・年功序列を三位一体の特徴としてきました。企業は一度正社員として採用したら定年まで雇用し続け、従業員は年齢とともに賃金が上がり、定年まで勤め上げるのが前提でした。しかしバブル崩壊以降の経済停滞やグローバル競争の中で、このモデルは維持が難しくなっています。
実際、経団連も2019年に「終身雇用を前提に企業運営を考えることには限界がきている」と公式に表明しました
経団連会長(当時)の発言では
就職時と同じ事業がずっと続くとは考えにくく、外部環境の変化で従来の終身雇用には無理が生じている
とされています。
トヨタ自動車の社長も同年に「日本では終身雇用の維持が難しい段階に来ている」と述べ、大企業トップが相次いで終身雇用制度の限界を指摘しました
また、年功序列についても見直しや崩壊が進んでいます。成果主義・実力主義への転換を図る企業が増え、定期昇給や役職の序列も絶対ではなくなりました
産業能率大学の分析によれば、「終身雇用と年功序列の崩壊」により若手時代の低賃金を中高年期に埋め合わせるという従来の構図も成り立たなくなり、20代・30代のうちから自分の貢献に見合った処遇を求める意識が強まっているといいます。実際、昨今では若手のうちに転職して他社で評価を上げようとする動きも一般化し、「ずっと勤めれば報われる」という保証は薄れています。
さらに、人員整理や早期退職募集が大企業でも珍しくなくなりつつあります。不況時には大企業もリストラを行い、「大企業だから安泰」という神話は既に崩れていると感じる若者も多いでしょう。こうした雇用システムの変化は、若者に会社への帰属意識より自身のキャリア自律を促す結果につながっています。事実、調査では大手企業の新入社員で自分が定年まで今の会社にいるイメージがある人はわずか20%程度しかおらず、残り8割は「いつかは転職する」と考えていることが示されています。
会社の側も従業員を守りきれない、従業員も会社に居続けるつもりはない——この相互不信のような状況では、「大企業に入ったからもう安心」とは到底思えないわけです。
働き方の多様化:フリーランス・副業・リモートワークの影響
近年のテクノロジー発展や制度改革により、働き方は多様化の一途をたどっています。フリーランスという選択肢は大きく広がり、日本でもその人口は定義によって数百万から千万規模に増加しています
かつては正社員として企業に属さなければ安定収入を得にくい状況でしたが、今やITエンジニアやクリエイターを中心に独立して働く若者も増えました。クラウドソーシングやオンラインマーケットの普及により、会社に属さずとも稼げる可能性が広がったことは、「大企業=安定」の図式を相対化しています。
また、日本政府は副業解禁を推進し、2018年に厚生労働省がガイドラインを公表して企業に副業容認を促しました。その結果、多くの大企業が就業規則を見直し、社員の副業・兼業を認め始めています。調査によれば、「勤め先で副業が認められている」社員の割合は27.5%と年々増加傾向にあります
副業を実際に行う若手社員の中には、本業以外で自分の興味関心を満たしたりスキルアップを図ったりするケースも多く、「会社一筋」ではないキャリア観が一般化してきました。「収入源を一つに頼らない方が安心」「会社に万一があっても副業が保険になる」という意識も広がりつつあります。
さらに、リモートワーク(テレワーク)の普及も働き方に大きなインパクトを与えました。新型コロナウイルス禍のピーク時には、日本全体で在宅勤務をする人の割合が一時3割を超えたとの調査もあります
コロナ収束後は一部で出社回帰の動きもありますが、それでも「場所に縛られない働き方」は多くの若者に経験され、今後の働き方の選択肢として定着しました。リモートワークによって地理的条件は重要度を下げ、地方移住や海外リモート勤務なども現実的な選択となっています。これらは個人が会社の枠にとらわれずキャリアを築くことを後押しする流れです。
働き方の多様化により、若者にとって大企業でフルタイム正社員になることだけがキャリアのゴールではなくなりました。「自分らしい働き方」への志向が強まる中で、たとえ大企業に入社しても「他にも道はある」「一社に依存しすぎるのは危険かも」という考えが頭をよぎるのは不思議ではありません。こうした環境では、会社の看板だけに安心を感じることは難しく、むしろ自分の市場価値を高め続けることや複数のキャリアパスを持つことが安心材料だと捉えられるようになっています。
自己実現・ウェルビーイング志向と大企業勤務のギャップ
現代の若者は仕事において自己実現やウェルビーイング(心身の健康や幸福)を非常に重視します。前述のようにZ世代は仕事の意義や社会貢献度を重んじており、またプライベートの充実やメンタルヘルスにも敏感です。働き方改革やコロナ禍も相まって、ワークライフバランスへの関心は高く、「多少収入が減っても無理なく働ける方がいい」「自分の好きなことができる時間を確保したい」という声も珍しくありません。

こうした志向に対し、伝統的な大企業の職場文化や仕事の在り方がミスマッチを起こすことがあります。例えば、大企業では部署間の分業が細かく若手の裁量範囲が限定されがちで、「社会的インパクトを実感しにくい」「自分が歯車の一部に過ぎないと感じる」といった不満が生じることがあります。また、旧来型の上下関係や意思決定の遅さから、「挑戦したいのに提案が通らない」「新人が意見を言い出しにくい雰囲気だ」と感じる若者もいます。実際、年功序列的な一括管理の下では若者の新しい発想や技術を活かしにくく、責任あるポストに就くまで10~20年待たねばならなかったとも指摘されています。
このような環境では、成長意欲の高い若手ほどフラストレーションを感じ、「この会社にいて自分は本当に成長できるのか?」という疑問を抱きがちです。
またウェルビーイングの観点でも、大企業勤務が必ずしも安心とは言い切れません。確かにかつては「大企業なら福利厚生も充実し、定時で帰れて有給も取りやすい」と言われましたが、実際には部署や職種によって忙しさは様々です。近年は労働時間の是正が進み若手の残業は大きく減少しましたが
その一方で「ゆとりある職場で物足りなさを感じる」という皮肉な声も出ています。いずれにせよ、若者にとっては職場の雰囲気や心理的な安心感も重要であり、それが欠けていると会社規模に関係なく不安を感じるものです。
要するに、若者は大企業に入れば物質的・経済的な安定は得やすいと理解しつつも、精神的・内面的な充実とのギャップに悩むことがあります。「安定したけど退屈」「恵まれているはずなのに幸せを感じない」という状態では、「安心」どころか自己喪失感さえ生まれかねません。若者にとっての安心とは“自分らしくいられること”でもあるため、その点で折り合いがつかない限り、たとえ大企業に属していても不安や不満が残るのです。
若者が抱える“不安”の実態と要因
では具体的に、現代の若者はどのような不安を抱えているのでしょうか。リクルートワークス研究所の調査によれば、近年の新入社員(2019~2021年卒)の75.8%が「自分は不安だ」と感じているといいます。この数値は2000年前後の新人世代(66.6%)や2010年前後(70.1%)と比べても高く、若手の不安感が増大していることを示しています。彼らが漠然と抱く「不安」の中身を探ると、現代ならではの傾向が見えてきます。

大きな要因の一つは、自分の将来像が描きづらいことです。終身雇用幻想が消えた今、「今の会社でこのまま働き続けていて、自分のキャリアは大丈夫か?」という根源的な問いが若者を悩ませています
実際、調査で「自分は別の会社や部署で通用しなくなるのではないかと感じる」と答えた新入社員が48.9%にも上りました。これは、現在の職場で身につくスキルや経験が汎用性を持つのか不安に思っている若者が半数近くいることを意味します。つまり、「会社にしがみつけなくなった時、他で通用する人材でいられるだろうか?」という自己不信・将来不安です。裏を返せば、彼らは常に自分の市場価値を意識しており、それを高め続けないと生き残れないというプレッシャーを感じています。この心理的不安は、終身雇用というセーフティネットが薄れた時代におけるサバイバル意識とも言えるでしょう。
また、前述したような「ゆるい職場」の存在も不安を誘発する一因です。古屋星斗氏は、自身の著書タイトルにもある「ゆるい職場」とは若手の能力や意欲に対して仕事の負荷が低すぎる職場だと述べています。
働き方改革で若手の労働時間が減り、有給も取りやすくなった結果、「職場が優しすぎて成長実感がない」という声も出ているのです。一見好ましい環境ですが、若者からすると「このまま楽な仕事ばかりしていて、自分は成長できるのか?」という不安につながります。皮肉にも、働きやすさの向上が若手のキャリア不安を高める側面も指摘されているのです。
さらに広い視野で見れば、グローバル化や技術革新のスピードが速い現代社会そのものが、若者にとっては将来予測の難しい不確実な世界です。社会学者のギー・スタンディングは、不安定な労働と生活を強いられる新たな階層を「プレカリアート(不安定階級)」と呼びましたが、その特徴は慢性的な不確実性と不安にさらされていることだと指摘しています。
日本に限らず世界的に見ても、就職氷河期やリーマンショック、パンデミックなどを経験した若者世代は、安定への信頼が薄く常に次の危機に備えねばという意識を抱えがちです。その意味で、「大企業に入ったからといって安泰ではない」という感覚はグローバル世代共通のものとも言えます。
以上のように、若者の不安は経済的な先行き(会社がずっと存続するのか、自分は食べていけるのか)と、職業人的な成長(自分はこのままでいいのか、通用するのか)の両面から生じています。心理学的には、自己効力感(自分は有能でやっていけるという感覚)の不足や、帰属不安(どこにも居場所がないのではという不安)として表れることもあるでしょう。社会的には、過去の日本では会社が提供していた「所属と保障」を、自分で確保しなければならなくなったことが不安の背景にあります。
まさに「若者だけに考えさせてはいけない」問題として、社会全体で支える仕組み作りも問われていると言えます。
現代における「安心」の再定義:何をもって安定とするか
以上の分析を踏まえると、「現代における安心」を再定義する必要性が浮かび上がります。かつて安心の代名詞だった「大企業に入って定年まで勤め上げる」モデルは崩れ、若者自身もそれを信じていません。では、21世紀のキャリア社会において、若者にとっての「安心・安定」とは何なのでしょうか。
一つキーワードとなるのは、「エンプロイアビリティ(雇用され得る能力)の確保」です。米国の組織社会学者カンターは「終身雇用という従来のジョブセキュリティが消え去った現在、社員が安心を得られるのは自分の雇用されうる力(経験や技能)しかない」と指摘しました。まさに、日本の若者も同じ感覚を持ち始めています。リクルートワークス研究所の分析では、若手社員が職場にコミットするための要素として「心理的安全性」と並び「キャリア安全性」という概念が重要だとされています。
「キャリア安全性」とは「このまま今の会社で働いていれば自分は成長できる」「仮に別の環境に行っても通用するはずだ」という認識の度合いで定義され、これが高いほど若手の仕事へのエンゲージメントも高まるといいます。
要するに、自分のキャリア展望に対する納得感こそが新しい安心感なのです。
この考え方に立つと、現代の安心は個人の中に源泉を持つことがわかります。企業規模や肩書に頼った安心ではなく、自分のスキル・経験・人脈といった資産に裏打ちされた安心です。極端に言えば、「会社が潰れても他でやっていける」「一社にしがみつかなくても食べていける」という自信こそが安心の拠り所となります。実際、調査でも「現職を続けることで自分のキャリアがどう展開し得るのか納得し安心できて、初めて仕事に打ち込める」と指摘されています。
会社から与えられる安定ではなく、自ら築く安定(自己安定)が重視されているのです。
同時に、安心の質的側面も再定義が必要でしょう。物心両面の豊かさを求める若者にとって、安心とは単に雇用契約が続くことではなく、心身ともに健康でいられることや自分の人生をコントロールできている感覚を含みます。例えば、いくら大企業で解雇の心配がなくても、過労で健康を崩したり自己成長の実感がなければ、それは不安定な状態です。逆に、中小企業やフリーランスでも自分らしく働けて将来の展望が持てているなら、それは安心と言えます。要は、現代の安心=自分の人生のハンドルを握れていることだと言えるでしょう。
最後に、社会的なセーフティネットも含めた安心の再構築も議論すべきです。若者の不安が個人の努力だけでは解決しにくい以上、企業も従業員のキャリア形成を支援し、社会も失業保険や学び直し支援などを充実させる必要があります。若者自身も社内外の機会をフル活用し、「社内キャリア」だけでなく「社外でも通用するキャリア」を意識的に築くことが重要です。それこそが“自分だけの安定”を手に入れる戦略であり、現代的な安心の形だと言えるでしょう。
結論
「大企業に入れば安心」という旧来の常識は、もはや現代の若者には当てはまらなくなりました。若者は価値観の変化と社会構造の変容の中で、新しい安心のかたちを模索しています。それは、一社に依存しないキャリア自律や、自分の成長実感、そして多様な働き方の中で得られる心の安定です。現代における安心とは、肩書や所属による受動的な安定ではなく、個人が能動的に築く安定へと再定義されつつあります。不確実性が常態化した時代だからこそ、若者たちは会社ではなく自分自身を信頼の拠り所にすることで、逆説的に安心を手に入れようとしているのです。
今回取り上げたように、日本・海外を問わず若者のキャリア観は変化し、「安心」の意味も拡張しています。大企業も終身雇用神話に代わる新たな心理的契約を模索し、若者の不安に寄り添うマネジメントが求められるでしょう。個人としても、学び続けスキルを磨くことや多様な経験を積むことで、自らの安心材料を増やしていくことができます。現代における“安心”とは何か?――それは、一言でいえば「変化に対応できる自分」であり、そのような自己を育むことこそが、若者にとって真の安定への道筋なのかもしれません。
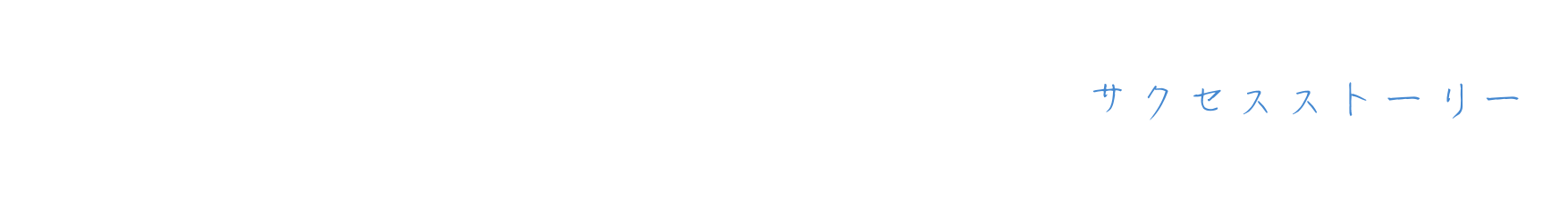



コメント