「高学歴=仕事ができる」とよく考えられていますが、これは本当に正しいのでしょうか?実際にはこれは相関関係であり、直接的な因果関係ではありません。この記事では、国内外の先行研究を交えて丁寧に解説していきます。
相関関係と因果関係の違い
まず、「相関関係」と「因果関係」の違いを理解しましょう。
- 相関関係とは、2つの要素の間に統計的な関連性はありますが、一方が他方を引き起こしているわけではありません。
- 因果関係とは、一方の要素が直接他方を引き起こしている関係のことを指します。
例えば、「アイスクリームの売上と熱中症患者数」は相関していますが、これは暑さという共通の要因があるためです。学歴と仕事の成功についても同様のことが言えます。
海外の先行研究
Duckworthら(2007)のGRIT研究
Angela Duckworth教授らは、「GRIT(やり抜く力)」がIQや学歴よりも仕事の成功を強く予測することを示しています。GRITとは「長期目標に対する情熱と粘り強さ」のことです。
Heckman教授(2008)の非認知能力研究
ノーベル経済学賞を受賞したJames Heckman教授の研究によると、学歴やIQ(認知能力)よりも非認知能力(社会性、忍耐力、協調性)の方が将来の成功に重要であることが明らかになっています。
国内の先行研究
情報技術者の学歴と企業規模に関する研究
本研究は情報技術者の労働市場において、学歴と企業規模がキャリアや離職行動にどのような影響を及ぼしているのかを分析したものです。1980年代から2000年代以降を比較し、データをもとに情報技術者の離職率や企業規模との関連性を調査しています。
主な結果として、
- 学歴が高いほど大企業に入職する傾向が強くなるが、学歴自体がキャリアの安定性や成功に直接影響を与えるわけではない。
- 企業規模が大きいほど離職率は低く、小規模企業ほど離職率が高い傾向が明らかになった。
- 情報技術者のスキル形成は入職後の企業内で行われる傾向があり、入職前の学歴は離職やキャリア形成に直接的な影響はない。
これにより、情報技術者市場において「高学歴=仕事の成功」という単純な因果関係は成立せず、学歴は企業規模と密接に関連しているが、キャリアの安定性や成功には直接的な影響を及ぼしていないと示されています。
高学歴が仕事もできるように見える理由
次の要素は、高学歴の人が「仕事ができる」と見える理由ですが、実際には直接の因果関係ではなく、単なる相関関係にすぎません。
- 採用時の学歴フィルター
企業は最初から高学歴の人を優先的に採用するため、職場に高学歴者が多くなり、結果的に「仕事ができる人=高学歴」という印象になりやすいのです。 - 勉強で身についた習慣や計画性が役立っている
高学歴の人は、受験勉強などを通じて計画性や良い習慣を身につけています。これらの習慣が仕事の成果に結びつきやすいため、高学歴の人が能力的に優れているように見えるのです。ただ、こうした習慣は学歴に関係なく誰でも身につけられるものです。 - 教育や研修が整った企業に入りやすい
高学歴の人ほど、教育・研修制度が充実した大企業などに就職しやすくなります。そのため、入社後にしっかりと研修を受けられ、スキルが伸びやすくなります。こうした企業環境が、「高学歴=仕事ができる」という印象を生んでいるのです。
このように、高学歴であることと仕事の能力には、隠れた要素が絡んだ相関関係があるだけで、学歴そのものが直接的な原因になっているわけではありません。
高学歴でも仕事がうまくいかないケース
以下のような場合には、高学歴でも仕事で成功するとは限りません。
- 主体性や行動力が不足している
- コミュニケーション能力が十分でない
- 柔軟性や応用力が低い
これらの能力不足は、学歴とは直接関係がありません。
まとめ
高学歴と仕事の成功には相関がありますが、直接的な因果関係はありません。
- 非認知能力(GRIT、コミュニケーション能力、チームワーク)が仕事の成果により大きく影響しています。
- 学歴だけで将来の成功を予測することは難しく、実践的なスキルや人間的な能力を磨くことが重要です。
大切なのは、学歴だけに頼らず、職場で必要とされる具体的な能力を身につけることが重要ですね。
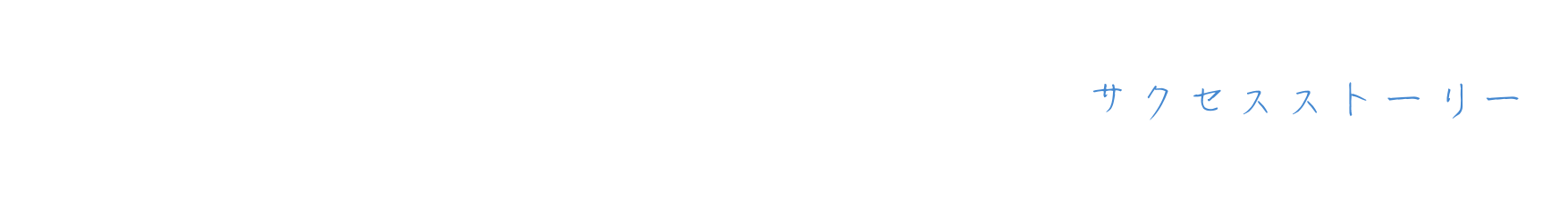
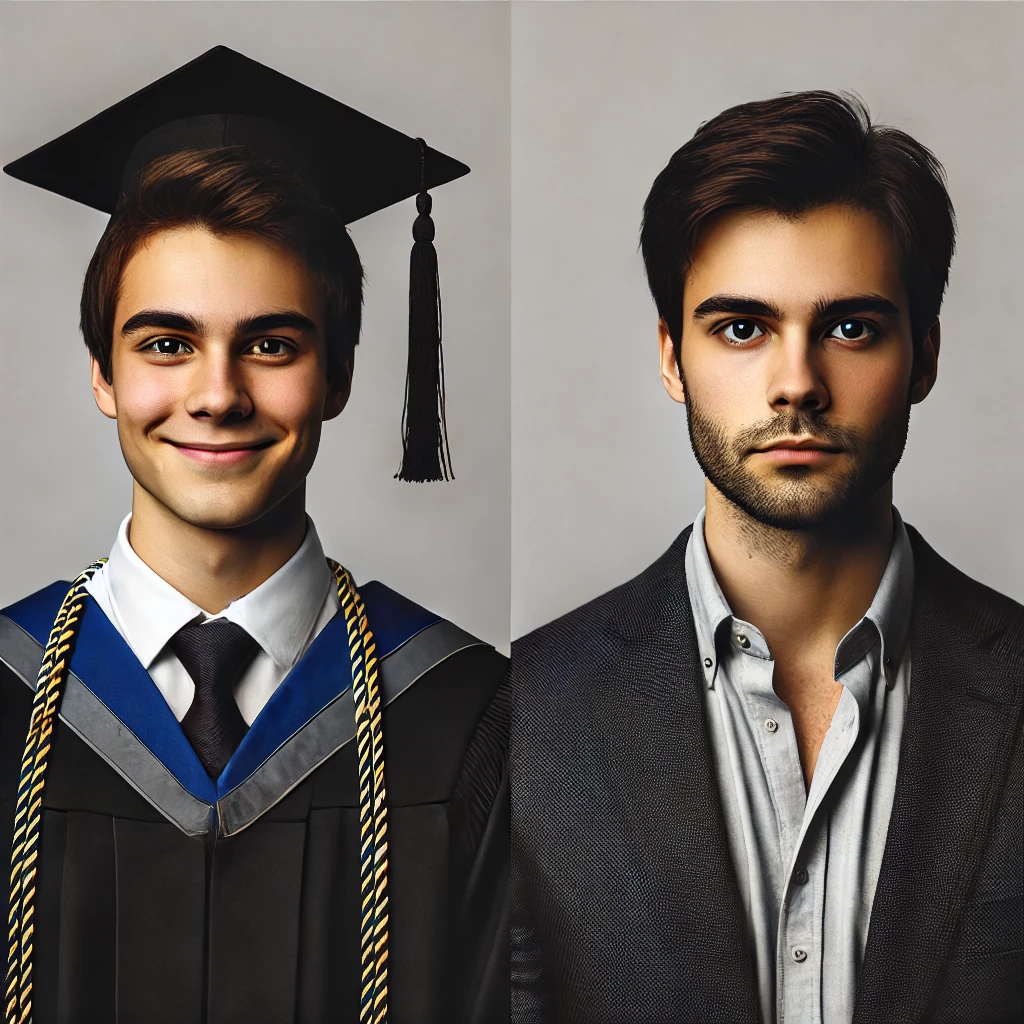


コメント