「えっ、こんなに税金戻ってくるの?」
そんな経験はありませんか?税金の制度は複雑で、知っている人だけが得をし、知らない人は気づかぬうちに余計にお金を払っていることもあります
今回は、年収500万円前後の方(若手社会人からシニア世代まで)に向けて、知らないと損する税金の落とし穴5選をカジュアルに紹介します。実際の生活で「これ知ってるだけでこんなに違うの!?」という具体的なポイントばかりです。それぞれ「なぜ損なのか」「どう対策するのか」をわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までチェックしてください。
では早速、あなたもハマっていないか確認していきましょう!
落とし穴1:医療費控除の見逃しで払い過ぎ
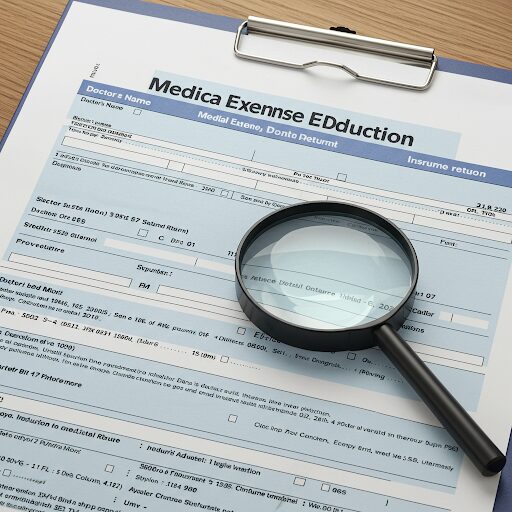
大きな医療費を払った年に確定申告をしないと、本来戻ってくるはずの税金が戻ってきません。会社員の多くは年末調整だけで納税が完了しますが、医療費控除(いりょうひこうじょ)は自分で確定申告しないと受けられない代表例です。医療費控除とは、1年間(1月〜12月)の本人や家族の医療費合計が10万円を超えた場合(※所得が200万円未満なら所得の5%超)に、その超えた分を所得から差し引ける制度です。
例えば年間で医療費を15万円支払った場合、超過分5万円について所得控除(所得から差し引く)を受けられます。課税所得が5万円減れば、その分の所得税・住民税(合わせて約20〜30%)に相当する1〜1.5万円程度の税金が戻ってくる計算です。これを知らずに何も手続きしないと、払い過ぎた税金をそのままにして損をしてしまうことになります。
【具体例】インフルエンザにかかって高額の治療費を払った、家族の手術でまとまった出費があった、出産で病院に支払った費用が多かった…こうしたケースでは医療費控除のチャンスです。通院のための交通費や市販薬代など「治療のため」の費用も含めて計算できます。健康診断自体は対象外ですが、その健診で重大な病気が見つかり治療に至った場合は健診費用も含めてOKです。
意外と対象範囲が広いので領収書はしっかり保管しておきましょう。
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。会社員の場合、翌年の2〜3月に税務署へ申告すれば還付を受けられます(還付申告といいます)。医療費の明細書に領収書の内容をまとめて記入し提出しますが、最近は領収書そのものの提出は不要になり、手続きはかなり簡単になりました。国税庁のサイトから作成して郵送したり、スマホで電子申告(e-Tax)することもできます。なお、年間の医療費が10万円に満たない場合でも、一定の条件下でセルフメディケーション税制(市販薬を年間12,000円超購入した場合の控除)という特例制度を使える場合があります
自分や家族の医療費がかさんだ年は、「もしかして医療費控除が使えるかも?」と必ず思い出して、申告によって払い過ぎた税金を取り戻しましょう。
落とし穴2:ふるさと納税を利用しないと損!
テレビやネットで話題のふるさと納税。実は「おいしいお肉やお米などの特産品がもらえるお得な寄付制度」くらいにしか思っていないと、大きなメリットを見逃して損しています。ふるさと納税は簡単に言うと、自分が選んだ自治体へ寄付をすると、寄付額のほとんどが翌年の税金から控除(減額)される仕組みです(自己負担2,000円を除く)
つまり2,000円の負担で寄付先の名産品がもらえるのが最大の魅力です。年収500万円程度の会社員であれば、家族構成にもよりますが年間およそ4.4万〜6.1万円まで寄付しても2,000円しか自己負担になりません。例えば上限5万円の方が5万円寄付すれば、5万円相当の特産品がもらえ、翌年の所得税・住民税が合わせて4万8千円減る(=結果的に自腹2千円)というわけです。ふるさと納税をしないということは、このおトクな機会を丸ごと逃していることになります。
また、ふるさと納税を上限額以上にしすぎてしまうのも損につながります。上限額を超えた寄付分については税金が控除されず、全額自己負担となってしまうからです。「返礼品につられてつい寄付しすぎたら、結局高い買い物になってしまった…」なんてことにならないよう、必ず自分の上限額の目安を確認しましょう。
年収や家族構成で上限額は変わりますが、インターネット上のシミュレーターやふるさと納税サイトで簡単に計算できます。逆に言えば、上限額内の寄付であればやらなきゃ損です。
ふるさと納税は各自治体のポータルサイト(楽天ふるさと納税など多数あります)から簡単に申し込めます。自治体から後日送られてくる「寄付受領証明書」は大切に保管しましょう。会社員の方で寄付先が5自治体以内なら、確定申告不要で控除が受けられるワンストップ特例制度も使えます(寄付時に申請し、各自治体に書類郵送するだけ)。ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例は無効になるため、寄付分も含めて確定申告すれば同じ控除が受けられます
いずれにせよ手続きは難しくないので、「まだやったことがない」という人は早速トライしてみましょう。注意点として住宅ローン控除を受けている人は要チェックです。住宅ローン減税(税額控除)との組み合わせによっては、ふるさと納税(所得控除)をしすぎると住宅ローン控除の枠を残して所得税がゼロになり、控除しきれない減税枠が出る可能性があります。年収が比較的低めで住宅ローン減税を受けている若い世代は特に気をつけましょう
適正な上限内で賢く利用すれば、やらないと大損な制度であることは間違いありません。
落とし穴3:「配偶者控除の壁」を知らずに損をする
結婚して配偶者(夫または妻)がいる人に関係するのが配偶者控除です。配偶者控除とは、収入の少ない配偶者を扶養している納税者(主に世帯主)に対して適用される所得控除で、配偶者を養う負担を軽減するための制度です。具体的には、配偶者の年間所得が一定額以下であれば、所得税の計算上、所得から最大38万円差し引ける控除が受けられます。(住民税では33万円控除)。この38万円控除によって所得税・住民税が軽減され、年収500万円のケースなら合計でおよそ10万円前後の税負担減になるため、適用できればかなり大きな節税になります。
ではどんな場合に配偶者控除が受けられるのかというと、ポイントは配偶者(扶養される側)の年収です。一般的に「103万円の壁」と呼ばれるものがありますが、これは配偶者の年収(給与収入)が103万円以下であれば配偶者控除が満額受けられる、という目安ラインです。給与収入103万円から給与所得控除(55万円※)を差し引くと所得が48万円となり、この48万円以下であれば配偶者控除OKという計算です
逆に言うと、配偶者の収入が103万円を1円でも超えると配偶者控除の適用外となり、納税者(夫や妻)はその年は38万円の控除を受けられなくなります。知らずに配偶者のパート収入が103万円を少しだけ超えてしまった場合、「ちょっと超えただけ」で数万円の税負担増になってしまい、損した…となりかねません。
もっとも、103万円を超えたら即大損かというとそうでもありません。実は**「配偶者特別控除」**という制度があり、配偶者の年収が約201万円まで段階的に控除が受けられる仕組みになっています。つまり年収103万円を少し上回った場合でも、すぐに控除がゼロになるわけではなく、配偶者特別控除として配偶者の収入に応じた控除額が差し引かれます(配偶者控除38万円がだんだん減っていき、年収201万円で控除ゼロになるイメージです)。とはいえ、配偶者の収入が低いほど有利なのは事実なので、この「壁」の存在を知らないと働き方で損得が生じる可能性があります。「せっかく稼いだのに手取りが減った」「もっと働けたのに控除を気にしすぎて収入を抑えてしまった」など、どちらでも損をしてしまうことがあるのです。
まずは配偶者の収入見込みを毎年チェックしましょう。パートやアルバイト収入であれば月収8万6千円程度を超えると103万円超えが見えてきますので要注意です。年の後半で「このままだと103万の壁を超えそう」と判明するケースも多いので、事前にシミュレーションして勤務日数を調整するなどの対策が考えられます。また、配偶者の収入がもし大きく増える見込みであれば、あえて控除を気にせず働いてもらった方が世帯全体ではプラスになる場合もあります。例えば配偶者がパート収入を103万円から130万円に増やせるなら、配偶者控除38万円は受けられなくなりますが、その分の収入増(+27万円)は税負担増(数万円)を差し引いても手取りでプラスになるケースが多いです。ポイントは「壁」を正しく理解してプランを立てることです。さらに最新トピックとして、2025年から税制改正でこの「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上げられる予定です。
これは扶養内で働ける収入上限が実質20万円アップするということで、より働きやすくなります。こうした制度変更もニュースなどで注目しておくと良いでしょう。配偶者控除は節税に直結しますから、自分の家庭が当てはまるかどうか知らないともったいないですよ。
※給与所得控除…給与収入から差し引けるみなし経費。最低55万円(令和2年以降)。給与収入103万円の場合は55万円の給与所得控除が差し引かれ、残り48万円が給与所得(課税上の所得)となります。
落とし穴4:扶養控除の申告漏れで家族扶養の恩恵を逃す
扶養家族がいるのに申告していないと、受けられるはずの扶養控除を逃して損をします。扶養控除とは、養っている親族(16歳以上の子どもや両親など)がいる場合に、一定額を所得から差し引ける制度です。先ほどの配偶者控除は配偶者限定でしたが、扶養控除はそれ以外の親族が対象です。特に見落としがちなのが年老いた両親や別居の親を扶養しているケースです。「別々に暮らしている親は扶養に入れられない」と思われがちですが、実は仕送りなどで生計を維持していれば同居していなくても扶養親族にできます。
例えば地方の実家の親に毎月仕送りをしている場合や、遠方の親の医療費や介護費用を負担しているような場合は、その親を税法上の扶養に入れることが可能です。
扶養控除の控除額は扶養親族の年齢等によって異なります。ざっくり言うと、対象親族1人あたり38万円(これが基本)、扶養親族が19〜22歳の学生なら63万円、同居の親など70歳以上の直系尊属なら58万円、別居の70歳以上の親なら48万円といった具合です。
かなり大きな控除額ですよね。例えば70歳以上の親を扶養に入れた場合、少なくとも年間48万円の所得控除が受けられます
年収500万円クラスであればこれによる所得税・住民税の軽減額は年間にして10万円以上になることも珍しくありません。仮に5年間見落としていたとすれば、累計50万円以上もの税金を余計に払っていた計算にもなりかねません。親を扶養に入れ忘れる=大損につながる可能性があるのです。
では誰でも親を扶養に入れられるかというと、条件があります。扶養に入れる親側の所得が年間48万円以下であること、が一つの目安です。
年金生活の親であれば、公的年金収入がだいたい158万円以下なら所得48万円以下となり扶養対象になりえます(65歳以上の場合、年金収入158万円≒所得48万円)。逆に言えば年金がそれなりに高額な場合や他に収入がある場合は扶養控除は受けられません。もう一つの条件は「生計を一にしていること」です。これは同居でなくても仕送りや生活費負担があれば満たせます。例えば毎月仕送りをしている、介護施設の費用を負担している、といった場合です。
現在ご自身が扶養している家族がいるか確認しましょう。16歳以上の子ども(高校生以上)は年末調整で会社に申告すれば扶養控除が受けられます※。配偶者以外で見落としがちなのは親や祖父母です。特に社会人になりたての頃は親を扶養に入れる発想がないかもしれませんが、例えば親御さんが年金暮らしで収入が少ない場合、仕送りをするようになったタイミングで扶養控除を申請できます。手続きは会社員であれば年末調整の扶養控除申告書に記入するだけです。在職中でなくても、確定申告をすれば扶養控除を適用できます。また、過去に遡って申告し直すことも可能です。仮に「数年前から親に仕送りしていたのに扶養控除を全く申告していなかった!」と気づいた場合でも大丈夫。還付申告は5年以内の過去分まで手続き可能なので、過去にさかのぼって扶養控除を適用し、払いすぎた税金を返してもらえます。実際に親の扶養控除漏れで過去5年分をまとめて還付申告し、数十万円単位の税金が戻ってきた例もあります
忘れていた方は早めに手続きを検討しましょう。
※16歳未満の子どもは税法上の扶養控除対象にはなりません(代わりに児童手当が支給される制度になっています)。高校生以上の子が対象です。
落とし穴5:iDeCoを活用せず節税チャンスを逃す

将来のために貯蓄や投資をしていますか?老後資金づくりと節税を同時にかなえてくれる制度がiDeCo(個人型確定拠出年金:イデコ)です。しかし「なんだか難しそう」「60歳まで引き出せないんでしょ?」と敬遠しているとしたら、実は大きな税金のメリットを取り逃がしています。iDeCoの最大の特徴は、掛金の全額が所得控除になることです。
毎月一定額を積み立てていくと、その合計額が丸ごと所得から差し引かれます。例えば年収500万円の会社員が毎月2.3万円(年間27.6万円)をiDeCoで積み立てた場合、所得税・住民税の減税効果は年間で約55,200円にもなります。なんと毎年5万5千円もの税金が減る計算で、10年間続ければ55万円以上節税できることになります。仮にもう少し少額の毎月1万円の積立でも、年間12万円積み立てて約2万4千円の税負担減という試算があります。
このように、iDeCoを使わないと将来のためにコツコツ積み立てながら税金を安くできるチャンスを逃してしまうことになるのです。
さらにiDeCoには他にもメリットがあります。運用益(利息や運用益)は通常20%課税されますが、iDeCo口座で運用した利益は全て非課税で再投資されます
将来60歳以降に受け取るときも年金や一時金として税制優遇措置があります。つまり拠出時・運用時・受取時の3段階で税優遇がある制度なのです。これらを総合すると「やらないともったいない!」と思えてきませんか?
iDeCoは20歳以上60歳未満で一定の収入がある人なら誰でも加入できます(会社員、公務員、自営業、専業主婦(※条件あり)などそれぞれ掛金上限は異なります)。証券会社や銀行などを通じて口座を開設し、毎月5,000円から積み立て可能です(掛金は1,000円単位で設定可)。
会社員の場合、勤務先にiDeCo加入の申請書を書いてもらう必要がありますが、難しいものではありません。積み立てた掛金は年末調整や確定申告で「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除として申告します。そうすれば所得税・住民税が確実に減額され、節税分のお金が手元に残ります。掛金の運用商品(投資信託など)は自分で選べますし、運用益は非課税なので長期運用すればするほどメリットが大きいです。注意点として、原則60歳まで引き出せないので無理のない範囲で掛金設定すること、口座管理手数料が金融機関ごとに違うので比較して選ぶことなどがあります。しかし、それを差し引いてもiDeCoの節税メリットは非常に大きい制度です。
特に年収500万円前後の現役世代にとって、利用しないのは損と言えるでしょう。もしまだ始めていないなら、老後の自分へのプレゼントだと思って検討してみてください。
なお、NISA(少額投資非課税制度)も投資の利益が非課税になるお得な制度です。こちらは所得控除こそありませんが、2024年から制度が拡充され一生涯で1800万円までの投資利益が非課税になる強力な仕組みになりました。将来資産形成をするならNISAも活用しないと損と言えるでしょう。税金面の優遇策は知って使えば家計の味方になってくれます。ぜひアンテナを張って、お得な制度を漏れなく活用してください。
チェックリストまとめ ✅ 知らないと損するポイントはココ!
- 医療費控除:年間10万円超の医療費がかかったら放置せず確定申告。払い過ぎた税金を取り戻そう
- ふるさと納税:自己負担2千円で特産品ゲット&税金軽減!上限額内で活用し、控除漏れしないようワンストップ特例も賢く利用
- 配偶者控除:いわゆる「103万円の壁」に注意。配偶者の収入に応じて控除を最大限受けられるよう調整を。2025年からは壁が123万円に拡大予定
- 扶養控除:別居の親でも仕送り等で扶養に入れられる!親の年金収入が約158万円以下なら扶養控除のチャンス。過去5年分まで遡って還付申告も可能
- iDeCo:老後資金づくりしながら毎年しっかり節税。掛金全額が所得控除で、年収500万円なら毎月2.3万円積立で約5.5万円の税金減。使わなきゃもったいない!
知らなかった制度や控除はありましたか?税金の落とし穴は知っていれば怖くありません。今日知った知識をぜひ生活に役立て、あなたも「賢い節税術」で損しないお金ライフを送りましょう!
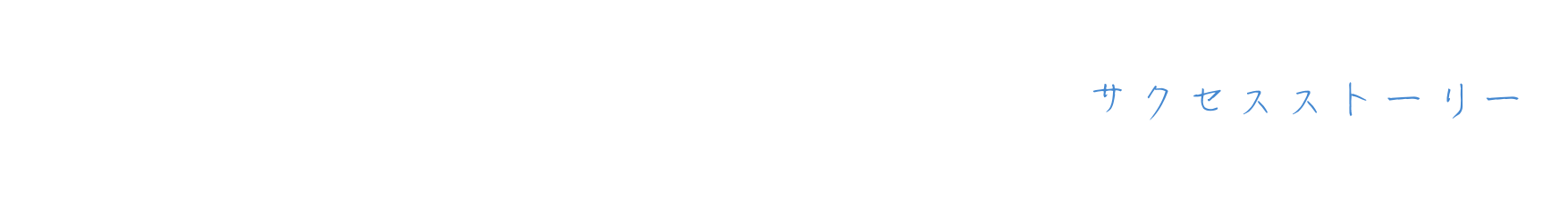
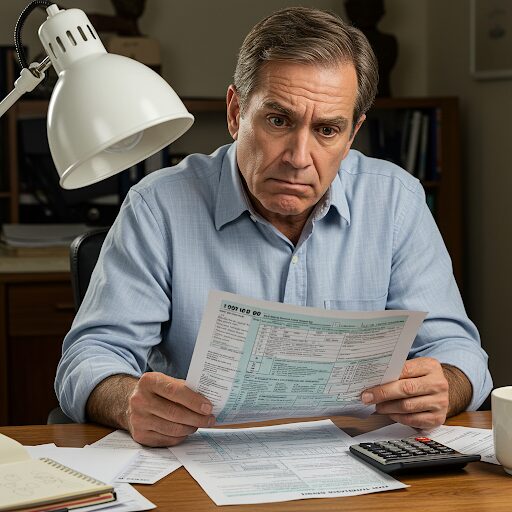


コメント